イラスト:立原圭子
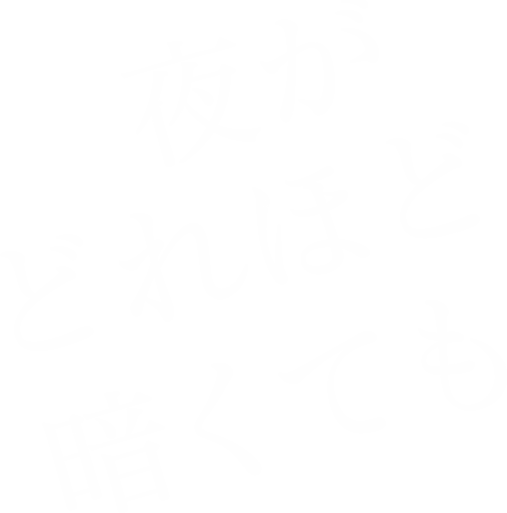

イラスト:立原圭子


作家デビュー10周年を迎え、
いよいよ活躍の場を広げる中山七里!
マスコミの真実をえぐる迫真のストーリー
奪われた幸せの先に見える真実の光とは?



上川隆也演じる主人公・志賀は、スクープを追う有名週刊誌の副編集長。 仕事ぶりを評価され、順風満帆なジャーナリスト人生を歩んでいたが、ある日、事態は一変する。一人息子の健輔がストーカー殺人事件を起こし、被害者とともに自ら命を絶ったのだ。スクープを追う側だった志賀は、一転、追われる立場となる。凶悪事件の容疑者家族として、世間からバッシングを受ける日々。まさに絶望の淵に立たされる中、ある出来事をきっかけに事件の真相に迫っていくことになる。少しずつ浮かび上がっていく新しい真実。そして、深い闇の中で志賀が見つけた、一条の光とは。この物語は、単なる転落劇ではない。男の慟哭と執念が引き起こす、奇跡の物語だ。
2020年11月22日(日)放送スタート![第 1 話無料放送]
毎週日曜日よる 10 時 WOWOWプライムにて放送(全 4 話)

―今回のドラマ化は単行本の刊行直後の四月にお話があったと伺いました。
中山七里(以下、中山)わずか一か月ですからね。さすがにここまでのスピードというのはなかったので驚きました。私の原作の映像化では最短記録です。文庫化も急遽決まり先月出ましたが、単行本発売から半年ということで、角川春樹事務所さんでもこれまでにないことだそうですよ。
―異例続きですね。
中山まぁ、こういうのもあっていいのかなと思っています。
―今年はデビュー十周年ですしね。その制作発表の際に「意図的にタブーとされるテーマを選んだので映像化は難しいだろうと思っていた」とコメントされていました。これは、そう簡単にドラマ化されてたまるかみたいな気持ちも内心はおありだったのかなと感じたのですが……。
中山全作品がそうです。別にひねくれて言っているわけじゃないんですよ。映像化を意識しながら書くより、映像化を拒んだ作品のほうがスケールが大きくなるような気がするんです。映像化を考えるとテーマは絞られてくるし、主人公の活動範囲も狭まってくる。となると、物語はどんどん縮小されていきます。それは面白くないですよ。いろんなことを自由に考えたい。だから、映像化を前提として書いたことはありません。
―では、映像化をOKするポイントはどこにあるのでしょうか。
中山書くまでは僕のものなんです。でも、本になったら、それは版元のものであり、読者のものだと思っています。ですから、映像化に関してOKだとかNGだとか口を出すということはしません。
―さすがに台本は気になるのでは?
中山いえ、こちらも同様ですね。原作者としていろいろ言ったほうがいいのかもしれませんけど。でも、出来上がったシナリオに目を通しても、まるで別の物語を読んでいるような感覚です。海堂尊さんが、映像化作品は孫みたいなもんだとおっしゃっていました。子どもじゃなくて、責任感の外れた孫だと。言い得て妙だなと思います。
―今回は報道サスペンスドラマと銘打たれています。小説にはいくつかのテーマがあり、その一つとして事件報道を巡ってのタブーとされる部分もリアルに描かれていましたが、そのタブーをクローズアップするような切り口ですね。
中山これ、地上波では無理でしょ。つまり、WOWOWさんしかできない。となれば、こうした切り口になるのは当然ですよね。むしろ、地上波でドラマを作っている方々がこれを見てどういう風な感想を持たれるのか。それが楽しみでもありますね。
―ディテールもいくつか変更されています。事件の真相に新たな視点が加わるなどドラマオリジナルの設定もあるようですが……。
中山まったく気にしません。先ほど申しましたように、自分の手を離れたらまったく別ものだと思っています。それにね、日頃から映画とか見てるとわかるんですよ。原作者が口出しして成功した例は少ないとね(笑)。
―主演の上川隆也さんについて伺います。その名前を聞き、安心したとおっしゃっていましたね。『テミスの剣』がドラマ化された際にも主人公の渡瀬を演じられていますが、どんな役者さんと映っているのでしょうか。
中山どんなことがあってもぶれない。そんなタイプの役者さんのように思います。おそらく、ご本人の中に揺るぎない演技プランの立て方というものがあり、そのとき必要とされる軸足を見つけることができるのでしょう。いわゆる演技派と呼ばれる方々はそうだろうと思うし、上川さんもそのお一人であると思います。
―小説は志賀が登場しないページがなく、志賀の物語として展開しています。それだけにドラマでは主人公という役割以上の重要性を感じます。
中山おっしゃるようにこれは個人のドラマです。今回は四話の放送になるわけですが、その全編にわたり引っ張っていく主人公ですから、よほどの力がないと演じきれない。上川さんのお名前を聞いたとき安心したというのはそういう理由なんです。四話、つまり四時間くらいのドラマを一人で引っ張るというのは、いまどきあまりないんじゃないかと思いますよ。二人組だったり、数人のグループで動かしていくのが主流でしょ。
―ほかにも個性的な役者さんが揃っていますが、気になる方はいますか?
中山井波を演じてくださる加藤シゲアキさんですね。アイドルから出発されて俳優もされ、小説家という一面も持っておられますよね。ただ、僕の中で印象深いのは、『犬神家の一族』などで金田一耕助を演じられたということ。その加藤シゲアキさんが僕の映像化作品に加わってくださる。感慨深いものがあります。やっぱりね、ミステリーが好きな人間としては横溝正史さんなどの作品がドラマや映画になれば、その都度見てしまうんです。
―ちなみに、書かれているときに登場人物の容姿のイメージなど持たれているのですか。
中山ないですね。ただ、その名前を見ただけでどんな人間かイメージしてもらえるようにしたいから、主人公の名前などは何よりも時間を掛けて考えます。でも実は、書いていて一番しんどいのがこの名前を考えることなんだけど(笑)。
―志賀の名前はどんな思いから?
中山志賀倫成という男は、どこか傲慢で固定観念で固まっているところがある人物として描いています。それが徐々に変わっていくんですが。でね、初めて言いますが、志賀直哉さんからいただきました。もちろん尊敬する作家ですし、作品も好きなんですが、僕としては納得できないなと思うことが一つあって。「富士山を見なければ、富士山は書けない」というようなことをおっしゃっているんですよね。
―なるほど。想像を執筆の源とされる中山さんならではですね(笑)。最後に、OAを待つ読者に一言お願いします。
中山このたびドラマ化されることになった『夜がどれほど暗くても』ですが、ランティエでも続編オファーをいただきました。今プロットを立てております。こうご期待!
この『夜がどれほど暗くても』を読んでみると、自分の吉本興業時代のことを思い起こさずにはいられなかった。私は二〇一五年に約三十五年間勤めた吉本興業を退社した。この小説の主人公は週刊誌の副編集長だ。夜討ち朝駆けしてスクープを探しまくった人物だ。私は吉本興業時代に広報を担当し、トラブルシューティングからのマスコミ対応が主な仕事だったので、この小説の主人公とは反対側の立場にいた。取材する側とされる側で向き合っていたと言える。
新卒で入った吉本興業で、私もこの小説の主人公のように仕事漬けの日々を送ってきた。しかし私は会社を辞めた。
やりたいことは大体やった上で、今後は自分のマネジメントは自分ですると決心し、「仕事」が私を支配していた生き方を見直したのである。現在は「謝罪マスター」を名乗り、企業のリスクマネジメントを担当している。「謝罪はゴールではなく、ゴールに向かうための道具の一つである」として、単なる謝罪のやり方とは違うコミュニケーションの方法を説いて回っている。
ただ退社した今も、吉本興業在籍時から続けている仕事が一つだけある。刑務所における「満期釈放者指導導入教育」である。それは罪を犯した人に対して、出所後に再犯を犯さないようにする教育担当者としての仕事である。ちなみに「満期釈放者」とは懲罰が多く身柄引き受けもなく、仮釈放もかなわない受刑者のことを指す。
経費節減が叫ばれる昨今、「仮釈放」ならば経費の削減にもつながる。税金を使って矯正教育を受けさせているわけだから当然だ。しかしそんな中で私が受け持つのは仮釈放もかなわない受刑者に対しての教育だ。それぞれが満期釈放で娑婆に戻る手前約一ヶ月間、社会復帰の訓練をするのだ。
私の受け持ちではないが、一見、意外な授業もある。電車の自動改札機の利用方法やスーパーマーケットで販売している野菜の値段などを教える授業だ。長期の受刑者は移り変わりの激しい現代社会に適応できないのだ。私の通う刑務所の収容者約千人のうち、六割が八年以上の懲役、一割が無期懲役となっている。
その人たちの出所前に、私が「コミュニケーション」の授業を行っている。授業の中身は、例えば受刑者が自分自身を知るための「自分へのインタビュー」、即興的な対応力を養うための「なぞなぞ教室」などがある。基本となるのは他人との会話のコツをつかむことといえるだろうか。謝罪したくてもできない人に謝罪の定義を教えたりもしている。このあたりは「謝罪マスター」の面目躍如というところだろう。
そんな受刑者たちへの授業の中で知った現実が一つある。
「皆さんの家族・親戚・友だちは被害者なのか加害者なのか?」という質問をしたときのことである。受刑者たちは「自分のせいで、自分の家族・親戚・友だちに迷惑を掛けたので被害者です」と答える。
「では、実際の被害を受けた被害者やその家族からは皆さん(加害者)の家族・親戚・友だちはどう見られているのか?」という質問にはみなが口をつぐんでしまう。どの表情も「そんなことを考えたこともなかった」と不安げだ。そこで私はもう一度問う。
「実際の被害者サイドから見たら、あなたの家族・親戚・友だちはどう見られていると思いますか?」
すると何人かの手が挙がる。「加害者だと見ていると思います」と。
その通りである。事件には何の関係がなくても被害者家族は加害者家族のことを加害者と同等に見ているのである。
そして本作、中山七里さんによる『夜がどれほど暗くても』である。主人公である「週刊春潮」の副編集長、志賀倫成は芸能界の不倫の暴露などエグい記事をスクープしては売上を上げ、その出版社の屋台骨を支えているという自負がある。
私の吉本興業時代の視点で見たら、「許せない! 人でなし! 大嫌い!」と言いたいのがそういった編集者たちだった。芸能プロダクションの広報にすれば「タレントや芸人、何ならあなたも誰も脛には傷を持ってるだろう!」と言いたいところだが、週刊誌はそこだけをえぐって来るし、そこに向き合うのが私の吉本興業時代の仕事だった。
スキャンダルが発覚したとき、記者に直接会って、相手がどこまで事実を知っていて、どこまで書こうとしているのかを探り、話の流れによっては文調を和らげてもらうために交渉したものだ。時には他の情報をバーターにすることだってある。
そこがコミュニケーション力の見せどころだった。
この作品では、ある日突然、志賀の大学生の息子・健輔がストーカー殺人を犯した上に自死したという事件が起きる。有能な記者だった彼は一夜にして加害者家族となってしまったのだ。
人生の激変によって、取材する側から取材される側になってしまった志賀。その上に左遷。「春潮48」への異動もあり、身も心もボロボロになる。私も過去の体験からちょっと意地悪を言うと「ざまぁ見ろ!」という気分だ。「追う側が追われる側に回ったときに感ずることが何か分かったやろ!」という気持ちである。
そんな中、彼は真実を知りたい一心で周辺の取材を続ける。私の吉本時代の仕事とは真逆であるが、そこに彼の記者としての矜持もまた立ち現れてくるのを感じた。
一方、被害者家族として両親を一度に喪い、ひとり残された中学生の奈々美は、誰に相談すればいいのか、何にぶつければいいのかも分からず、荒んだ自宅で生きている。学校生活も虐めにあい、私でさえ何とかしてやりたくなる痛々しさに溢れていた。加害者家族である志賀を憎まざるを得ない心情が、展開していくところに目を見張った。
英語の諺で言うところの「He who hates Peter harms his dog」(ピーターを憎む人は、彼の犬を傷つける)だろうか。
事件小説などにおいては、普段は「加害者」と「被害者」が話題の中心になるが、この本はあえて「加害者家族」と「被害者家族」といういずれも残された者を主役としている。先に書いたが「謝罪」は「ゴール」ではない、「ゴール」という両者の落とし所を模索し、そこに向かっていくために必要なコミュニケーションが謝罪なのだ。
本作にも奈々美の苦しみとして描かれるが、現在のネット社会でのSNSの世界ではリアル界とは少し違った「被害者」と「加害者」が存在する。それは顔も見えない住所も年齢も性別も識別できない「自称被害者」が、失敗した者、事件を起こした者を「加害者」と設定して攻撃してくる。「炎上」というやつだ。
このネットバッシングは匿名を原則としてやって来るので、なかなか対処も謝罪もやりようがない。もっと言えば本当の謝罪の相手ではない場合もある。いま私はおおつねまさふみ氏の「MiTERU(ミテル)」というインターネットの炎上対策会社の顧問もさせてもらっている。ネットバッシングという嵐が吹き止まぬ中、誹謗中傷や風評被害と向き合うのは困難極まりない。この小説で、志賀が奈々美への虐めに身体を張って対処していったように、ネット上での危機管理もまた変わっていくのだろう。
志賀の人生も仕事に支配されていた。インターネットという新たな環境の下で、読者にもいるに違いない仕事人間が、今後も自分で自分自身を上手く乗りこなし、公正さを持ち続けて生きていけるだろうか。彼らがどこに光明を見出すのか、ブレーキを踏まずに読んでしまった一冊だ。
【解説者紹介】
竹中功(たけなか・いさお)
吉本興業株式会社入社後、宣伝広報室を設立し、月刊誌「マンスリーよしもと」初代編集長を務める。よしもとクリエイティブ・エージェンシー専務取締役などを経て2015年7月退社。著書多数。